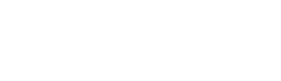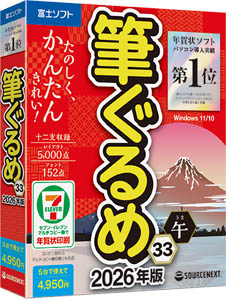寒中見舞いの書き方と注意するべきポイントまとめ

寒中見舞いとは
寒中見舞い(かんちゅうみまい)は、日本の慣習の一つで、二十四節気の小寒(1月5日頃)から立春(2月4日頃)までの寒中に行う見舞いである。 現在では、豪雪地帯・寒冷地での相手を気遣う手紙等を指す。 また年賀状の返答や喪中のため年賀状が出せない場合の代用にも使う。
引用:寒中見舞い
書く際、注意するポイント
出す期間
松の内が過ぎてからの(1月7日頃)から立春(2月4日頃)までが寒中見舞いを出す期間となっています。
相手に7日に届くようにするならば、5,6日に出すとちょうどいいかもしれませんね。
また、2月4日を過ぎてしまうと、暦の上では春になります。
これ以降に出す季節の便りは、また名前が変わって「余寒見舞い」というものになります。
文面も変化するので注意してください。
用途による書き方の違い
寒中見舞いとまとめて言っても、様々な用途により書き方が異なります。
あなたがどんな内容の寒中見舞いを出したいかによって、文面が変化します。
以下は寒中見舞いでの用途の一覧になります。
- 一般的な季節の便り
- 喪中と知らずに、こちらから年賀状を送ってしまった場合のお詫びとお悔やみ
- 喪中はがきを頂いた方へ、年頭のご挨拶に変えて
- 相手の方が、こちらの喪中を知らずに年賀状が送られてきた場合の、喪中の報告のため
- 年賀状を頂いたのに、こちらから松の内の間に出しそびれた場合
- 年賀状を出した後にお歳暮が届いた場合のお礼として
このように、同じ寒中見舞いでも比べてみると書く文面が違うのが分かりますよね。
あなたが送りたい寒中見舞いは何か?をよく考えましょう。
寒中見舞いの書き方
では、どんな用途の寒中見舞いを書くかが定まったとして、次に構成を見てみましょう。
寒中見舞いは主に3つの構成でできています。
(1)季節の挨拶
1つ目は季節の挨拶です。これはほとんど、どの寒中見舞いも同じで、定型文としてある程度決まっているものになります。
例えばですが、
「寒中お見舞い申し上げます」
「寒中お伺い申し上げます」
「余寒お伺い申し上げます」
などになります。
(2)本文
次に本文になります。こちらは先ほどの用途によって変化するので、注意してください。
本文の最初に、寒さに対しての相手の健康の気遣いを入れるのが、一般的となっています。
(3)日付
最後に日付を入れましょう。
こちらは漢数字で書くようにしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
寒中見舞いを書いたことがない方も、今後書く機会もあるかと思います。
ある程度の常識として寒中見舞いの知識を頭に入れておきましょう。
最新版 『筆ぐるめ』は・・・
「公式 販売代理店サイト」で最新版の『筆ぐるめ』をご購入いただけます。